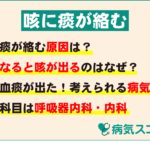まいこぷらずまはいえんマイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎とは?
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニエという細菌による感染症です。
一年中感染の可能性がありますが、冬に感染者が増える傾向です。感染すると風邪とよく似た症状を発症します。しかし、風邪のように回復せず、咳や熱が長引きます。
若年層に多くみられる肺炎でもあります。
かつて、日本では4年おきに大流行していて、流行年が夏季オリンピックの年に重なっていたことから「オリンピック熱」と呼ばれることもありました。
しかし、1984年(ロサンジェルス五輪)、1988年(ソウル五輪)の年に大流行して以降、特にオリンピック開催年だけ流行するという傾向は見られなくなっています。
マイコプラズマ肺炎が疑われる場合、成人であれば呼吸器内科、子供なら小児科を受診しましょう。咳が長引いている場合などは、マイコプラズマが原因かもしれません。肺炎の疑いがあると診断されれば、X線検査や血液検査などの検査を受けて詳しくしらべることになります。
マイコプラズマ肺炎は「第三種感染症」
マイコプラズマ肺炎は、学校保健安全法における「第三種感染症」に指定されています。
医師が「感染の恐れがない」と認めるまでの期間、幼稚園・学校などは出席停止になります。
・第一種感染症
完全に治癒するまで出席停止。
エボラ出血熱、ペスト、重症急性呼吸器症候群(SARS)などが該当します。
「第一種感染症の感染者がいる家に住んでいる場合」「第一種感染症の流行地域を旅行してきた場合」なども出席停止になることがあります。
・第二種感染症
病状により、学校医・医師が感染の恐れはないと認めるまで出席停止。
たとえば、インフルエンザなら「発症後5日が経過していて、なおかつ解熱から2日(幼児は3日)が経過していること」が出席停止を解除する条件です。
麻疹(はしか)、水疱瘡(みずぼうそう)など、ほかの第二種感染症も、出席停止期間の基準が決まっていることが多いです。
第一種感染症と同じく、「第二種感染症に感染した家族と同居している場合」「第二種感染症が流行している場所に滞在していた場合」なども出席停止になることがあります。
・第三種感染症
病状により、学校医・医師が感染の恐れはないと認めるまで出席停止。
コレラ、細菌性赤痢などのほか、「(条件によっては出席停止になる)そのほかの感染症」という項目が存在します。
この「そのほかの感染症」に含まれるのが、マイコプラズマ感染症です。手足口病、ヘルパンギーナなどが同じ項目に含まれています。
第一種・第二種と異なり、「家族が感染している」「流行地域に行ってきた」などの理由で出席停止になることはありません。
子供がマイコプラズマ肺炎と診断された場合は、原則として出席停止になります。
出席停止期間が明確に定められているわけではありませんが、一般的には「解熱から2日経過するまで」を出席停止とします。
咳が1か月続くこともあるので、厳密には長期間にわたって病原体を排出する恐れがあります。
しかし、1か月も出席停止にするわけにはいかないので、「病原体の排出量が多く、感染の恐れが強い期間」を出席停止扱いにしています。
- 目次
マイコプラズマ肺炎の症状
発熱や全身倦怠感、頭痛、痰を伴わない咳など発症直後は、風邪と区別がつきません。
ただ、幼児に比べて小学生以上では重症化しやすく、場合によっては40℃以上の熱が出る場合もあります。必ずしも「風邪と同じようなもの」とは限らないので、軽視することは避けましょう。
また、いったんは熱が下がっても、その後、再び発熱する場合があります。熱が上がったり下がったりを繰り返す「弛張熱(しちょうねつ)」になることもあり、症状は長引きがちです。
咳が出はじめるのは、体調不良を自覚してから3~5日後が多く、最初は乾いた咳(痰の絡まない咳)が出ます。時間が経つごとに咳は悪化する傾向にあり、だんだんと湿った咳(痰が絡む咳)に変わっていきます。
多くの場合、熱が下がったあとも3~4週間にわたって咳が続きます。個人差はありますが、咳が特にひどくなるのは、発症から2週目です。
マイコプラズマ感染症を起こした子供の25%が嘔吐・下痢などの消化器症状をきたすとされています。
鼓膜炎・中耳炎などを起こして「耳が痛い」と訴える人もいます。そのほか、発疹・筋肉痛・関節痛が出ることもあります。
▼マイコプラズマ肺炎に子供がかかったときの対処について詳しく知りたい方はこちら
ベビママほっと。:マイコプラズマ肺炎は子供にうつりやすい?相談できる全国の小児科情報もご紹介
潜伏期間
細菌・ウイルスなどの病原体に感染してから、症状が出るまでの期間を潜伏期間と呼びます。マイコプラズマ肺炎は潜伏期間が長く、だいたい2~3週間程度です。
潜伏期間が長いことから、「職場・学校などの空間で流行しやすい」という特徴を持っています。潜伏期間が2~3週間ということは、「感染者は2~3週間にわたって、自覚がないまま通学・通勤を続ける」ことを意味します。
肺炎としては症状が軽い場合も多く、風邪だと思って通学・通勤を続ける人も多くなります。そのため、職場・学校など閉鎖空間で流行する傾向があります。
さらに、発症から治癒するまでにも時間がかかり、咳が止まるまでには平均して3~4週間ほど必要になります。
マイコプラズマ肺炎は症状に個人差があり、中には2~3日でほとんど治まる人もいます。逆に1か月以上が経過しても、まだ咳が出る場合もあります。
類似した症状の病気
多くの場合、マイコプラズマ肺炎の特徴は「風邪に似た症状」と「長引く咳」である。
同じような特徴を有する病気がほかにもあるので、きちんと判別する必要がある。
1.結核
結核菌が原因となる感染症。初期症状は、咳・発熱など風邪に似ている。
良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、最終的には咳が悪化していく。
進行すると、咳と同時に血痰が出るなどの激しい症状が出る。
あわせて読みたい
2.百日咳
百日咳菌が原因の感染症。やはり、初期症状は咳・発熱・くしゃみなどで、風邪との区別は困難である。
だんだんと咳が悪化し、発作的に連続して咳をするようになる。
その後、咳は治まっていくが、最初に症状が出てから治癒するまでに2~3か月を要する。
あわせて読みたい
3.喘息(ぜんそく)
アレルギーによる症状であり、感染症ではありません。
咳・痰が出るほか、呼吸をするときに「ヒューヒュー」という喘鳴音(ぜいめいおん)がするのが特徴です。
あわせて読みたい
4.慢性閉塞性肺疾患(COPD)
動いたときに呼吸苦・咳などの症状が出ます。肺胞が破壊されることで、うまく呼吸できなくなっていきます。
ほとんどの場合、喫煙が原因と考えられています。実際、長年にわたって喫煙を続けてきた高齢者が発症する傾向にあります。
あわせて読みたい
マイコプラズマ肺炎の診療科目・検査方法
長引く咳などの症状があるときは、小児科、呼吸器内科を受診しましょう。
感染症迅速検査(専用キットによる検査)と遺伝子検査と血液検査(マイコプラズマ抗体検査)が行われます。
マイコプラズマ肺炎が疑われる場合、内科・呼吸器内科のいずれかを受診すると良いです。もちろん、お子さんの場合は小児科・小児内科を受診しましょう。
しかし、現実的には「マイコプラズマ肺炎の診断をしてほしい」という名目で医療機関を訪れる人はほとんどいません。「風邪をこじらせた」「咳が止まらない」などの理由で医療機関を受診した結果、マイコプラズマ肺炎と診断されることがほとんどです。
いずれにしても、風邪のような症状が出てから、「2週間以上、咳が止まらない」という場合は早めに医療機関を受診することが推奨されます。
風邪のような症状を訴えて受診すると、一般的には問診がおこなわれます。問診の結果、医師が「ただの風邪ではない」と判断した場合にだけ、詳しい検査を実施します。
感冒(風邪のこと:かんぼう)症状に対する問診
風邪の症状で受診した場合、たいていは次のような質問をされます。
・どれくらいの期間、咳が続いているか?
2週間を超えて咳が続いている場合、マイコイプラズマ肺炎や百日咳を疑います。
・持病を持っているかどうか?
喘息など、咳が出る持病の有無は診断において重要です。
・すでに処方を受けるなどして、抗菌薬を服用しているか?
マイコプラズマに有効な抗菌薬は限られています。「ある種の抗菌薬が効かなかった」という事実があれば、重要な情報になります。
・学校や職場での流行状況、家族の体調はどうか?
学校・職場・家族にマイコプラズマ肺炎の人物がいれば、感染が疑われます。
マイコプラズマ肺炎が疑われる場合の検査
マイコプラズマ肺炎をはじめ、感染症・肺炎が疑われる場合は、検査を実施することになります。主に、次のような検査がおこなわれます。
1.画像診断(胸部X線)
感染症を疑った時点で、通常は胸部レントゲン撮影をおこないます。
ただ、マイコプラズマ肺炎の場合、それほどはっきりとした影が映らないこともあります。むしろ、レントゲン撮影は「結核」や「(一般的な)肺炎レンサ球菌による肺炎」を見つけるのに向いています。
とはいえ、問診の時点では「結核の疑い」などもあり得るため、通常、まずは胸部レントゲンを撮影します。
2.迅速診断(PCR法)
患者の喉をこすって採取した「咽頭(いんとう)ぬぐい液」を使い、マイコプラズマが検出されるかどうかを調べる方法です。
20分ほどで結果が出るので有用だが、すべての医療機関で実施できるわけではありません。
3.核酸増幅法(NAT)(かくさんぞうふくほう)
「咽頭ぬぐい液」または「痰」を採取して、培養する方法です。培養した結果、マイコプラズマが検出されるかどうかを確認します。
検査結果を得るまでには早くても1週間ほどかかるので、臨床には向きません。
4.血液検査
血液検査で、マイコプラズマの抗体が出るかどうかを確認します。
ほかの細菌感染症では白血球の増加を認めることが多いが、マイコプラズマ感染症の場合、白血球は「正常値」または「低下」を示す傾向にあります。
マイコプラズマ肺炎の原因
非定型病原体(※1)―肺炎マイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae)に感染することで起こります。
マイコプラズマ肺炎の原因は、マイコプラズマと呼ばれる細菌です。
細胞壁を持たないことから普通の細菌より小さく、自己増殖できる微生物としては最小です。マイコプラズマの感染経路は、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染によるものです。
・飛沫感染
感染者の咳・くしゃみなどで病原体が飛散し、ほかの人に感染することを指します。多くの場合、1~2m以内の範囲で飛沫感染が起こります。
・接触感染
例えば感染者が病原体の付着した手で、ドアノブなどを触った時、もし、別の人物が同じドアノブに触り、その手で鼻・口に触れた場合、感染の恐れがあります。
モノに接触することで、間接的に病原体が移動します。
飛沫感染は「咳・くしゃみなどで病原体が飛散することによる感染」で、接触感染は「病原体の付着した手で鼻・口などを触ることによる感染」です。
接触感染の場合、「感染者が鼻水を拭った手でドアノブを触り、別の人が同じドアノブを触った手でサンドイッチを食べた」などのケースで感染することがあります。そのため、基本的にはインフルエンザ対策と同じ方法で予防することになります。
まずは、咳・くしゃみをしている人に近づくのを避け、外出時はマスクをすることが第一の予防策になります。また、手洗いはもちろん、「つり革・手すりなどを触ったら手指を消毒する」といった習慣も予防に役立ちます。
マイコプラズマに対しては、インフルエンザ対策に用いられるアルコール消毒のジェルが有効です。
潜伏期間が長く、肺炎としては症状が弱い場合もあるため、「感染者が無自覚に病原体を広げるリスク」があります。
特に潜伏期間は、何の症状もあらわれません。本人も自分が肺炎の病原体を持っているとは思わず、ふだんどおりに外出し、友人・知人と至近距離で会話をします。恋人・家族間などでは長時間にわたる接触があるため、さらに感染リスクが強まります。
マイコプラズマ自体は、あまり感染力の強くない病原体です。しかし、潜伏期間が長いことから、感染に気づかず、親密な人に感染させる恐れがあります。
親密な人同士で、長時間・至近距離の接触をすることを「濃厚接触」と言います。マイコプラズマ肺炎は、閉鎖空間での濃厚接触による感染が多いです。
マイコプラズマ肺炎の予防・治療方法・治療期間
マイコプラズマ肺炎は細菌感染症である。そのため抗菌薬を使用して治療します。
抗菌薬にはいくつかの種類があり、マイコプラズマ・ニューモニエに効果的な抗菌薬が選択されます。
一般的には、マクロライド系(※2)のエリスロマイシン(※3)、クラリスロマイシン(※4)などの抗生剤が処方されます。
一方で、一部の抗菌薬に対しては効果がありません。
さらに、近年では「抗菌薬の効きにくい菌―耐性菌」が発見され、従来使用されてきたマクロライド系抗菌薬という種類の薬にも効果がないことがあり、問題視されています。
治療の多くは抗生剤による治療を7日~14日間おこないます。
マイコプラズマ肺炎の原因菌―マイコプラズマは、細菌の仲間です。そのため、抗菌薬(抗生物質)を処方することで軽快が期待できます。
また、すべての抗菌薬が有効というわけではありません。
マイコプラズマは「細胞壁を持たない細菌」です。そのため、「細胞壁合成酵素を阻害する抗菌薬(β-ラクタム系抗生物質)」は無効になります。
もともと細胞壁を持たないので、「細胞壁を攻撃する作用」では意味がありません。
β-ラクタム系抗菌薬に該当するのは、たとえば「ペニシリン系」「セフェム系」の抗菌薬などがあります。
そこで、マイコプラズマ肺炎に対しては「マクロライド系抗菌薬」を第一選択とするのが一般的でした。
マクロライド系抗菌薬は細菌のタンパク質合成を阻害することで、増殖を抑えます。
耐性菌
1999年まで、「マクロライド系抗菌薬に耐性を持つマイコプラズマは存在しない」とされてきました。しかし、2000年頃から、マクロライド系抗菌薬が効かない耐性株が出現しています。
耐性株は増加の一途をたどり、2014年に発表された全国の65施設を対象にした調査において、2012年にマイコプラズマ感染症と確認されたのは349例、そのうち288例で耐性株が検出されました。
つまり、2012年の時点で、マイコプラズマの83%が「マクロライド耐性株」だった、ということになります。
近年は、「マクロライド系抗菌剤の効かないマイコプラズマ」の比率が大きくなっています。
マクロライド耐性マイコプラズマ感染症には、「テトラサイクリン系抗菌剤」「ニューキノロン系抗菌剤」が用いられます。
治療薬
マイコプラズマ肺炎に用いられる抗菌薬は、次の3系統です。いずれも、7~10日ほど処方するのが一般的です。
また、抗菌薬のほか、医師の判断で「咳止め」「解熱剤」など対症療法のための薬が処方されることもあります。
・マクロライド系
代表的な薬剤にはエリスロマイシン、テリスロマイシン、リンコマイシンなどがあります。
細菌のタンパク質合成を阻害して、増殖を抑えるため、このような殺菌ではなく「増殖を抑える」という働き方の抗菌剤を「静菌系抗菌薬(せいきんけいこうきんやく)」と呼びます。
・テトラサイクリン系
代表例はミノサイクリン、オキシテトラサイクリンなどの薬剤です。タンパク質合成を阻害して細菌の増殖を抑える薬であり、静菌系抗菌薬の1つです。
ただし、子供に用いると「歯の着色」など副作用が出る恐れがあるため、8歳未満には使用しません。
・ニューキノロン系
代表的な薬剤としてはレボフロキサシン、ナジフロキサシンなどが知られています。
細菌の「DNAジャイレース」という酵素を阻害する薬。細菌を死滅させる「殺菌系抗菌薬」です。
予防
極力、感染の可能性の飛沫感染や接触感染などをさけるための対策をします。
ただし、感染を予防するワクチンや予防接種などは存在しない。そのため感染の確率を大きく下げることは困難です。
マイコプラズマに対する特別な予防法はないので、風邪・インフルエンザ対策を徹底することが基本になります。
マイコプラズマ肺炎の治療経過(合併症・後遺症)
治療は可能です。しかし、免疫が生涯にわたり効果を発揮する病気ではありません。そのため何度でもかかる可能性があります。常に、感染予防を意識するべき病気の1つです。
世の中には「1回かかると、もうかからない病気」「免疫ができて、かかる確率が大幅に下がる病気」が存在します。
しかし、マイコプラズマ肺炎は複数回にわたって感染・発症の恐れがあります。
マイコプラズマに対する免疫は、生涯にわたって続くものではないので、時間が経つと再び感染する恐れがあります。
合併症
マイコプラズマ・ニューモニエが肺に感染した肺炎がマイコプラズマ肺炎です。その他の場所に細菌が感染するマイコプラズマ感染症には、注意するべき合併症が存在します。
そうした感染症性の疾患を合併する確率は高くはありません。
髄膜炎、脳炎、ギラン・バレー症候群など重篤な合併症も知られています。
主な合併症として、次の症状が知られています。
1.無菌性髄膜炎(むきんせいずいまくえん)
「髄膜(ずいまく)」は、脳・脊髄(せきずい)を保護するための膜です。
髄膜が炎症を起こすことを髄膜炎といい、「髄液から細菌が検出されない髄膜炎」を無菌性髄膜炎と呼んでいます。
マイコプラズマ感染に起因する髄膜炎は、無菌性髄膜炎となる。高熱に加え、頭痛・嘔吐などが主な症状です。
また、髄膜炎に特徴的な症状として、首の後ろ(うなじの付近)が痛み、首を前方に曲げられなくなります。
2.脳炎
脳炎は、脳が炎症を起こした状態。高熱・頭痛・嘔吐に加えて、意識障害・痙攣(けいれん)などの症状が知られています。
咳などの症状が出てから脳炎を発症するまでに数週間かかることが多く、脳炎の原因特定が困難なケースがあります。
3.中耳炎
マイコプラズマが気道を経由して、中耳に入ることがあります。
マイコプラズマに起因する中耳炎の場合、鼓室(鼓膜の奥にある空間:こしつ)に水が溜まる「滲出性中耳炎(しんしゅじゅつせいちゅうじえん)」を起こします。
3.ギラン・バレー症候群
筋肉を動かすための神経(運動神経)に障害が起きて、「手足に力が入らなくなる」「呼吸不全を起こす」などの問題が生じます。
はっきりとしたメカニズムはわかっていませんが、細菌感染症を起こしたあとにギラン・バレー症候群を発症する例が多いです。
マイコプラズマ感染症を発症してから数週間後に、ギラン・バレー症候群の症状が出る例があります。
マイコプラズマ肺炎になりやすい年齢や性別
年間で感受性人口の5~10%が罹患するとされています。小学校や中学校での流行が多く、7~8歳がピークになります。
子供・若い人の発症が目立ち、例年、マイコプラズマ肺炎にかかる患者の8割程度が14歳以下です。
一例として、2012年の年齢別報告数を確認すると、次のようになっています。
0~ 4歳 30.2%
5~ 9歳 31.4%
10~14歳 18.6%
15~19歳 3.4%
20~39歳 7.8%
40~59歳 3.3%
60歳以上 5.3%
圧倒的に若年者の発症が多く、20~39歳といった抵抗力の高い年齢層でも7.8%という高い数字です。
反面、60歳以上で5.3%と低く、高齢者の罹患率があまり高くありません。
本来、肺炎の原因菌として、もっとも一般的なのは「肺炎レンサ球菌」です。
肺炎レンサ球菌による肺炎にかかりやすいのは、「65歳以上の高齢者」と「5歳未満の乳幼児」です。
つまり、抵抗力の低い乳幼児・高齢者の罹患率が高くなります。
マイコプラズマ肺炎は「5~35歳」において主要な肺炎であり、肺炎レンサ球菌による肺炎とは異なる傾向があります。
編集部脚注
※1 非定型病原体
非定型病原体は、「β-ラクタム系抗菌薬で殺菌することができない細菌」です。
β-ラクタム系抗菌薬は「細菌の細胞壁を構成するペプチドグリカンの合成を阻害する薬」の総称です。
具体的には「ペニシリン系抗菌薬」「セフェム系抗菌薬」などが該当します。
マイコプラズマ肺炎の病原体―マイコプラズマ・ニューモニエは「細胞壁を持たない細菌」なので、細胞壁の合成を阻害しても意味がありません。
また、レジオネラ属の細菌は「細胞内寄生菌」であり、人間の細胞内で増殖します。
β-ラクタム系抗菌薬は細胞内にほとんど入らないため、細胞内寄生菌には効果が期待できません。
さらに、クラミジア属の細菌は細胞壁に「ペプチドグリカン層」がありません。
当然ながら、「ペプチドグリカンの合成を阻害する薬」であるβ-ラクタム系抗菌薬は無効です。
このような「β-ラクタム系抗菌薬が効かない細菌」を指して「非定型病原体」または「非定型細菌」と総称しています。
※2 マクロライド系
マクロライド系は、抗菌薬の系統の1つです。
細菌のタンパク質構成器官―リボソームの働きを阻害する薬です。
リボソームは2つのサブユニットにわかれており、細菌のリボソームは「30S」と「50S」から構成されます。
マクロライド系抗菌薬は、50Sと結合して、本来の働きができないように阻害します。
「細菌の増殖を抑える」という効き方をすることから、「静菌的に作用する」と表現されます。
ちなみに、人間のリボソームは「40S」と「60S」なので、マクロライド系抗菌薬の影響を受けません。
そのため、マクロライド系は「人間に対する毒性がきわめて低い抗菌薬」と見なされています。
※3 エリスロマイシン
エリスロマイシンは、マクロライド系抗菌薬の1つです。
1952年に精製された「最初のマクロライド系抗菌薬」になります。
抗菌スペクトルが広い(=さまざまな種類の細菌に効果的である)薬ですが、マクロライド系の中では副作用が強いとされています。
※4 クラリスロマイシン
クラリスロマイシンは、マクロライド系抗菌薬の1つです。
1990年に開発された薬で、副作用も穏やかになっています。
また、エリスロマイシンが1日4~6回の服用を要したのに対し、1日2回の服用で済むというメリットもあります。
マイコプラズマ肺炎は、発熱・咳・頭痛などの症状を引き起こす感染症です。「マイコプラズマ・ニューモニエ」という細菌に感染することで発症します。
風邪の症状に似ていますが、どんどん咳がひどくなります。咳は長引き、熱が下がってからも3~4週間ほど継続します。
執筆・監修ドクター

経歴2006年 近畿大学医学部卒業
東京都老人医療センター(現:健康長寿医療センター)初期研修医
2008年 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 後期研修医
2010年 日本医科大学付属病院 循環器内科入局 同大学院生、久保田クリニック副院長
2014年 日本医科大学付属病院 循環器内科助教
関連する病気
マイコプラズマ肺炎以外の病気に関する情報を探したい方はこちら。
関連カテゴリ
マイコプラズマ肺炎に関連するカテゴリはこちら。
関連コラム
「マイコプラズマ肺炎」に関するコラムはこちら。