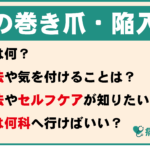外反母趾とは
外反母趾(がいはんぼし)は足の親指の付け根にある骨が変形し、親指が人差し指の方向へ向いていく病気です。
先端の細い靴やヒールを履く機会がある女性に多い病気で、悪化すると親指が人差し指の下にもぐり込んでしまったり、指の上に乗ったりしてしまうこともあります。
親指の付け根が靴に当たったり、親指と人差し指が重なったりしてしまうと痛みを伴うため、日常生活に支障をきたします。
外反母趾の種類
外反母趾には主に「靭帯性外反母趾」、「仮骨性外反母趾」、「混合性外反母趾」、「ハンマートゥ性外反母趾」、「病変性外反母趾」の5パターンがあり、それぞれ特徴が異なります。
1.靭帯性外反母趾(じんたいせいがいはんぼし)
足先のアーチ構造を支えている「横中足靭帯(おうちゅうそくじんたい)」という靭帯が緩むことで、親指が人差し指に向かって曲がってしまうのが特徴です。一般的な外反母趾のパターンといわれ、親指自体が大きく曲がってしまいます。
2.仮骨性外反母趾(かこつせいがいはんぼし)
親指はほとんど曲がっておらず、付け根の骨だけが異常に出張っていることで、曲がっているように見えてしまうのが特徴です。日常生活の中で足の指をうまく使えていない人に多く、後天的になってしまう外反母趾のパターンといえます。
3.混合性外反母趾(こんごうせいがいはんぼし)
靭帯性外反母趾と仮骨性外反母趾が合併している外反母趾のパターンです。靭帯性外反母趾の症状が進んで親指がうまく使えなくなることで、仮骨性外反母趾が引きおこされてしまいます。中高年以上の女性に多いのが特徴です。
4.ハンマートゥ性外反母趾(ハンマートゥせいがいはんぼし)
生まれつき足の指が長すぎる人に多く、指を地面につけることができない外反母趾のパターンです。指が長すぎるのが原因で、足の指をハンマーのように縮こまった状態(ハンマートゥ)にして歩くくせがついてしまっている状態です。「ハンマーのように縮こまった状態」とは、指がまっすぐ伸びず、足の裏側方向に丸まっている状態のことを指します。
5.病変性外反母趾(びょうへんせいがいはんぼし)
外反母趾によく見られる足の親指だけが変形するのではなく、足指全体が変形・脱臼している外反母趾のパターンです。関節が変形してしまうリウマチや、指の第一関節が太く変形したり骨自体が隆起(りゅうき)したりするヘバーデン結節、事故などによっておこります。病変性外反母趾は手術でしか治療できず、成功率が低いにも関わらず再発率が高いというのが特徴です。
外反母趾の症状
外反母趾は足の親指が人差し指に傾いている角度によって、初期・軽度・中等度・重度に分けられます。
- 正常値
外反母趾の角度は9度~15度 - 軽度の外反母趾
外反母趾の角度は20度未満 - 中等度の外反母趾
外反母趾の角度は20度以上40度未満 - 重度の外反母趾
外反母趾の角度は40度以上
初期や軽度の外反母趾の段階では、痛みや日常生活への影響はほとんどありません。20度以上の中等度になるにつれて親指がくの字に変形し、付け根が外側(反対の足の親指側)に飛び出します。中等度以上で靴を履くと、外側に飛び出した部分がこすれて痛みが生じます。
外反母趾は一度進行してしまうと元に戻すことが難しいので、普段から外反母趾にならないように予防をしていくことが大切です。
重症時の症状
外反母趾は放っておくと悪化し、歩くこともままならなくなったり、靴を履いていなくても日常生活の中で痛みやしびれが生じるようになったりします。親指の付け根の関節が脱臼してしまい、隣の指(人差し指)と重なってしまうこともあります。
外反母趾のチェックリスト
この症状に3個以上当てはまったら外反母趾かもしれません。医療機関を受診することをおすすめします。
□親指が小指の方に曲がっている
□親指のつけねが内側に張り出している
□親指のつけねが痛い
□親指のつけねが腫れて赤くなっている
□親指のつけねが靴に当たって痛い
□親指が第2指の下にもぐり込んで重なっている
□第2、3、4指が小指の方に曲がっている
□親指のつけねの関節の下が痛い
□第2指のつけねの関節の下が痛い
□足が平べったくなり先の方が広がっている
□扁平足になっている
□かかとが外側に傾いている
*このチェックシートは、医師の診察に代わるものではありません。セルフチェックの結果が問題なさそうな場合でも、少しでも不安を感じたり気になることがあれば、必ず医療機関にご相談ください。
*上記のチェックリスト以外にも、親指の角度にも注意が必要です。
親指の骨が人差し指側に15度以上傾いたら外反母趾の疑いがあり、20度を超えたら明確に診断がされます。
また、骨の角度が15度以下であっても痛みを感じる場合は、病院を受診します。
外反母趾の診療科目・検査方法
外反母趾の場合、整形外科を受診しましょう。主に問診や、レントゲンなどの画像検査などをおこなうこともあります。
問診
親が外反母趾かどうか
足の形は遺伝するため、外反母趾は女性に多いことから、母親や祖母が外反母趾になったことがあるかは診断のポイントになります。
先端が細い靴やハイヒールを履く必要のある職業についているか
靴の種類によっては足の親指を変形させ、外反母趾の進行や悪化を招くため必要な情報です。
痛みはあるか
中等度の外反母趾では痛みを伴うため、痛みの有無によって現在の程度や進行具合を判断する材料となります。
靴を脱いでいても痛むか
重度の場合は靴を履いていないにも関わらず痛みが出るため、保存的な治療をおこなうのか手術をするべきかの治療方法の選択につながります。
検査
外反母趾でおこなう検査には主に、「画像検査」と「フットプリント法」の2つがあります。
骨の角度や程度、体重がかかっている箇所を調べます。
1.画像検査
画像検査では正面と側面のレントゲン写真を撮影し、外反母趾の程度や骨の角度(脱臼の有無)、足のアーチ構造がどう変化しているかも併せて診ながら重症度を判断していきます。
画像検査は骨を詳しく診ることができるため、正確な診断をおこなうのに役立ちます。
2.フットプリント法
フットプリント法は、インクのついたフットプリンターの上に立ち、足裏で重点的に体重がかかっている箇所を調べるなど、足の状態を把握することができます。
プリント後の濃淡によって外反母趾や開帳足(かいちょうそく)、指が浮いているかなどを視覚的に確認します。
また、外反母趾の角度も同時に図ることができ、重症度を判断することが可能です。
放射線などを使用することもなく人体への影響が少ない検査方法といえます。
外反母趾の原因
外反母趾の原因には、歩き方のくせや履いている靴、筋力の低下などさまざまなものが考えられます。
1.歩き方やくせ
外反母趾の患者さんは歩き方に特徴があります。普段から足指を使わずに歩くくせが染みついているので、ペンギンのような「ぺたぺた歩き」が見られます。かかとから着地していないため、親指の付け根の部分に負担がかかりやすく、外反母趾を引きおこす要因となります。
2.合わない靴を履いている
サイズが合っていない靴や先端が細い靴、ヒールが高い靴などは足のつま先に負担がかかって外反母趾になりやすいです。
運動不足による筋力の低下も外反母趾の要因の一つです。土踏まずがないタイプのサンダルなどを履くことで足指を動かす筋肉が衰え、足のアーチが崩れることで結果的に親指の変形が進行する原因となります。
3.遺伝的要素やリウマチなど
生まれつき足の指が長い人は、ハンマートゥ性外反母趾になる可能性が高まります。
外反母趾には骨格遺伝の影響があるとの指摘があり、家族に外反母趾を発症している人がいる場合も注意が必要です。
リウマチなど、ほかの病気が原因で病変性外反母趾になるケースもあります。
外反母趾になりやすい足の形
人間の足の形には、「エジプト型」「ギリシャ型」「スクエア型」の3つがあり、外反母趾になりやすい型があります。
エジプト型
足の指の中で親指が一番長く、日本人に多いタイプです。親指が長いため外反母趾や足の小指が親指側に曲がってしまう内反小趾(ないはんしょうし)になりやすいといわれています。最も外反母趾になりやすいタイプです。
ギリシャ型
足の指の中で人差し指が一番長く、靴の中で折れ曲がって変形しやすいタイプ。人差し指が長いため第一関節が縮こまってしまう槌趾変形(つちゆびへんけい)になりやすいといわれています。ハンマートゥ性外反母趾を発症しやすいタイプです。
スクエア型
親指と人差し指がほぼ同じ長さで、別名「ゲタ足」とも呼ばれているタイプです。巻き爪やタコといった足のトラブルが多いといわれています。
外反母趾の予防・治療方法・治療期間
外反母趾でおこなわれる治療には、痛みの軽減を目的とした手術を伴わない「保存療法」と、骨の変形を治して痛みを取り除くことを目的とした「手術療法」の2つがあります。
基本的には保存療法から治療を開始し、改善しない場合や重度の外反母趾となっている場合には手術療法がおこなわれます。
1.保存療法
軽度から中等度までの外反母趾の治療には、主に痛みを軽減する保存療法をおこないます。保存療法には、「靴の指導」「運動療法」「装具療法」「薬物療法」の4つがあります。
靴の指導
靴の指導では、自分に合った靴を選んだり履いたりするための指導が受けられ、痛みの軽減や変形の進行の防止に役立ちます。初期段階で靴の指導がおこなわれるため、外反母趾の治療の中でも一般的な治療とされています。
また、小児期に足に合った靴を履くことで、外反母趾になるリスクを軽減できるとされています。
運動療法
運動療法では、足の指を曲げる、閉じる、開くといった外反母趾体操(グーパー運動)や、両側の親指にゴムバンドをつけて足先を開く体操をおこないます。体操をすることで外反母趾による痛みの軽減や、変形の矯正が期待できます。
外反母趾の患者は足の筋力が低下していることもあるため、足がつることがあります。繰り返しやることで筋力がつき自然とつらなくなっていきます。
歩行
外反母趾の原因の一つが歩き方にあることから、正しい歩き方をしっかりと学ぶことが重要です。かかとから地面につくように歩き、足の指先まで体重移動をおこない指で地面を蹴っていきます。
歩き方を正しくすることで足裏にかかる負担が分散され、外反母趾の防止と同時に胼胝(たこ)の予防にもなります。
足のストレッチ
外反母趾の進行を防ぐためには、自宅でもできる足のストレッチが推奨されます。左右それぞれの足指でグーチョキパーを作る「足指じゃんけん」や、足のアーチが崩れないようにつま先に体重をかけるつま先体操なども有効です。
足のストレッチは筋力アップとともに、足の機能回復の役割もあるため、時間を見つけて少しずつ実施することが重要です。
装具療法
装具療法では、足の親指と人差し指の間に外反母趾用の装具をつけたり、インソールなどを使ったりすることで足の変形を矯正する方法です。装具も親指の付け根の痛みを和らげるパッチや、夜間用、靴の中に入れるものなど、さまざまな種類があります。これらを患者の足の状態に合わせておこないます。
装具療法は装具自体の装着を中止してしまうと、効果は持続しないともいわれています。
薬物療法
薬物療法は単体ではなく、ほかの保存療法と併用されます。消炎鎮痛剤が入った湿布や軟膏、クリームなどの外用薬を使用することで、痛みを緩和します。薬物療法だけでは外反母趾の改善を見込むことはできないため、あくまで補助的な治療法です。
2.手術療法
保存療法をおこなったにも関わらず状態が好転しない場合や、痛みが強くて歩くこともままならないほどの重度の外反母趾には、手術療法を検討します。手術療法は主に、「近位骨切り術」「骨幹部骨切り術」「遠位骨切り術」「遠位軟部組織手術」があり、骨の変形具合や場所によって選択されます。
近位骨切り術
近位骨切り術は、外反母趾の手術でよくおこなわれる一般的な方法です。親指の根元にある第一中足骨の体の中心に近い部分を切除し、軸の位置を元に戻す矯正を実施します。手術後の経過も良好で重症度に関わらず実施され、年齢による制限もありません。
遠位骨切り術
近位骨切り術と並び、一般的な外反母趾の手術療法として用いられます。軽度から中等度に適用されることが多く、第一中足骨の体の中心から遠い部分を切除して矯正します。近位骨切り術と同様、年齢による制限はありません。
骨幹部骨切り術
第一中足骨の中央部分を切除して矯正をしていく手術療法です。中央部分を切除するためほかの手術療法と比べてより大きな矯正が可能です。中等度から重度の外反母趾に有効とされ、治療の経過は「近位骨切り術」や「遠位骨切り術」と変わらないといわれています。
骨幹部を切除するため骨が脆くなってしまう骨粗しょう症の患者は、医師への相談が必要です。
遠位軟部組織手術
遠位軟部組織手術は、保存療法にて改善が見られない軽度の外反母趾に適用されることが多いとされています。親指の筋肉の軟部組織を切り取って位置を矯正したり、関節を包む関節包を短く縫合し直したりする方法です。骨自体を切除する方法ではないため、ほかの手術療法と比べると矯正の程度は少ないです。
テーピングやインソールの使用
足裏のバランスを整えるため、テーピングやインソールを活用します。保存療法としてテーピングやインソールを用い、違和感が少ないうえに、痛みの軽減にも期待できます。
靴の中敷きとして使用するインソールには、地面から足へ伝わる衝撃を和らげることができます。
外反母趾の治療経過(合併症・後遺症)
外反母趾は一度進行してしまうと元に戻すことが難しい病気です。
普段から外反母趾にならないように予防をしていくことが大切です。
外反母趾が重症化すると痛みが出始め、運動不足に陥ってしまう可能性があります。そうなると痛みを軽減するための保存療法では対処することが難しくなり、手術をせざるを得ない状況になります。
運動不足が続いてしまうと足腰や背中の筋肉が弱まり、糖尿病や脂質異常症、心臓病、腰痛などを引きおこす原因となります。
外反母趾を放置し、重度の状態で痛みが強くなったり歩行がつらくなったりした場合は、骨や腱を切って指の位置を元に戻す手術が必要になります。
手術後はリハビリを避けることはできず、元のように靴を履いて歩けるようになるまでは2~3ヶ月ほど時間がかかります。
合併症
外反母趾によっておこる合併症には、「内反小趾」や「胼胝(べんち:タコ)」などがあります。
内反小趾
親指が人差し指側に曲がる外反母趾とは対称的に、小指が薬指側へ曲がって変形してしまう状態が内反小趾です。外反母趾とともに発症することが多く、先端の細い靴を履くことで悪化します。小指をうまく使うことができなくなるため体がぶれやすく、重症になると靴に出っ張った部分(小指の付け根の骨)が当たって歩くこともままならなくなります。
胼胝(べんち:タコ)
外反母趾によって正しい歩行ができなくなると、指の付け根を繰り返し打ち付けることになり、防御反応として皮膚の一部分だけが厚くなる胼胝が発生します。胼胝ができる部分は歩いている中でよく体重がかかる部分でもあるため、徐々に硬くなっていき歩いていると痛みを伴うようになります。
外反母趾になりやすい年齢や性別
発症年齢に関しては、日本の足部トレースを使用した研究より、幼稚園児から外反母趾が発見されています。また、小学6年生〜中学生では、男女ともに外反母趾の患者さんが発見され、女性の発症率が高いです。
国内でも海外でも女性に多いという調査結果が圧倒的に多いという報告があります。
また加齢により、外反母趾は進行する傾向があります。
参考・出典サイト
執筆・監修ドクター

経歴2005年 帝京大学医学部卒業
2012年 のぞみ整形外科内科クリニック開院
2017年 スガモ駅前整形外科開院
2020年 医療法人社団のぞみ会理事長
スガモ駅前整形外科 院長
のぞみ整形外科内科クリニック 院長
望クリニック 副院長
関連する病気
外反母趾以外の病気に関する情報を探したい方はこちら。
関連カテゴリ
外反母趾に関連するカテゴリはこちら。
関連コラム
「外反母趾」に関するコラムはこちら。