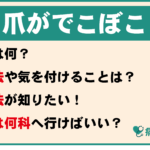あえんけつぼうしょう亜鉛欠乏症
亜鉛欠乏症の症状
亜鉛不足によりおこる症状はさまざまな種類があります。
代表的な症状は以下のとおりです。
①皮膚炎
乳幼児にみられやすい症状です。口や目の周りなどに発症し、水疱をともなう場合もあります。
褥瘡(床ずれ)にも関係しています。
②脱毛
後頭部から始まり、頭部全体に広がっていきます。また頭髪だけでなく眉毛なども脱毛します。
円形脱毛症の場合も血中の亜鉛濃度が低いことによる場合が多いです。
③発育障害・低身長
身長が伸びにくい、体重が増えにくいなどの症状が出ます。
症状は亜鉛を投与することで改善されます。
④性腺機能不全症
思春期までは、二次性徴がなかなかおこらないなどの症状が生じます。成人男性であれば精子減少、成人女性の場合は妊娠しにくくなるとされます。
⑤味覚障害
高齢者に多いです。金属味や苦味を訴えるといった症状があらわれます。
亜鉛欠乏症の診療科目・検査方法
診断のための検査として、血清亜鉛値が最も使用されています。基準値は80~130μg/dLとなります。
60μg/dL未満を「亜鉛欠乏」、60~80μg/dL未満で「潜在性亜鉛欠乏」と診断します。
診断基準は
①以下の1)、2)のうち1項目以上を満たしている
1)症状や所見があらわれている
臨床症状、所見:皮膚炎、口内炎、脱毛症、褥瘡、食欲低下、発育障害、性腺機能不全、易感染性、味覚障害、貧血、不妊症
2)血液検査の「血性アルカリホスファターゼ」の値が低い
②上記の症状の原因となる他の病気がない
③血清亜鉛値が60μg/dL未満
④亜鉛を補充すると症状がよくなる
以上の4つすべてを満たすと、亜鉛欠乏症と診断されます。
症状があらわれた場合、すみやかに内科、小児科などを受診する必要があります。
亜鉛欠乏症の原因
接種量が少ないというだけでなく、亜鉛を摂取しても吸収できていないという場合もあります。また体の亜鉛の必要量が普通より多くなっている状態になっているというケースもあります。また、接種量は十分であっても、排泄する量が過剰になっていることで亜鉛が不足していることもあります。
接種量が足りない原因としては偏食や少食などがあります。
亜鉛は動物性タンパク質に多く含まれているため、これらの摂取が少ない場合や、食事量そのものが少ない場合に生じやすくなります。
とくに女性の過度なダイエットによってもなりやすくなります。
また、乳児の場合は母乳に含有する亜鉛の不足により発症します。
吸収がうまくいかないケースとしては、腸から亜鉛の吸収がうまくできず、皮膚炎や下痢をする「腸性肢端皮膚炎(ちょうせいしたんひふえん)」の場合などがあります。
コーヒーやカルシウムは亜鉛の吸収を妨げるため、過剰に摂取すると亜鉛不足をまねきます。
亜鉛の必要量が増えるケースとしては激しいスポーツや肉体労働などの運動が原因になります。
肝臓病などの場合、尿から亜鉛の排泄が増えることもあります。
関節リウマチ、パーキンソン病、糖尿病、うつ病、てんかんの治療薬でも、排泄が増えます。
激しい運動をするアスリートでは、汗や尿から亜鉛が排泄され不足がちになります。
亜鉛欠乏症の予防・治療方法・治療期間
①食事療法
亜鉛を多く含む食品をよく摂取する方法です。
食品100gあたりで亜鉛が多い食品として、
牡蠣(13.2mg), 煮干し(7.2mg),ビーフジャーキー(8.8mg),豚レバー(6.9mg),パルメザンチーズ(7.3mg),ピュアココア(7.0mg),抹茶(6.3mg),カシューナッツ (5.4mg),ごま(5.9mg)などがあります。
しかし、食事療法だけでは改善しない場合が多く、薬物療法が必要です。
②薬物療法
「検査内容と主な診療科目」の項目で示した診断基準の①②③を満たした場合、亜鉛製剤の適応となります。
学童~成人では50~100mg/日、
幼児では25~50mg/日、
乳幼児・小児は1~3mg/kg/日
を経口投与します。
投与する薬は、酢酸亜鉛製剤(ノベルジン)が適応とされています。
治療期間は症状により異なりますが、低身長症では半年~1年、皮膚炎は1週周間程度で改善するとされています。
亜鉛欠乏症の治療経過(合併症・後遺症)
2016年、国内で初めて治療薬として「ノベルジン」が承認されました。これによって患者数が増えている中、今後の治療に大いに期待されています。
一方で、肝がん切除後の患者・前立腺がん患者では、亜鉛欠乏が生存率を低下させる報告があります。
予後に影響するため、早期に治療が必要です。
亜鉛欠乏症になりやすい年齢や性別
2003年の全国調査で推定24万人に味覚異常があると報告されています。その中に多くの亜鉛欠乏による患者さんが含まれていることになります。
発症しやすいのは、乳幼児と高齢者です。
乳幼児の場合、成長のために日々細胞分裂を繰り返すため、亜鉛不足になりやすいため注意が必要です。特に低出生体重児(2500g未満)になりやすい傾向があります。
高齢者は、先にも述べたように薬を服用している人が多く、薬に亜鉛の吸収を妨げるものが多いことによって症状があらわれます。
男女差は特になく、2015年の国民健康・栄養調査報告では男女共に摂取量は少なく不足気味でした。
参考・出典サイト
執筆・監修ドクター

経歴1998年 埼玉医科大学 卒業
1998年 福岡大学病院 臨床研修
2000年 福岡大学病院 呼吸器科入局
2012年 荒牧内科開業
関連する病気
亜鉛欠乏症以外の病気に関する情報を探したい方はこちら。
関連カテゴリ
亜鉛欠乏症に関連するカテゴリはこちら。
関連コラム
「亜鉛欠乏症」に関するコラムはこちら。