はったつしょうがい発達障害
発達障害(はったつしょうがい)は生まれつきの脳機能の発達のかたよりが原因でおこる障害です。
得意なものと不得意なものの差が大きく、広い範囲におよんで目立ちます。なにかの物事に対して適切に行動することができなかったり、対人関係がスムーズにいかなかったりするため、社会生活のなかで困難が目立つ障害です。
発達障害はいくつかのタイプに分類されています。そのなかでも代表的なものは自閉症スペクトラム障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害などがよく知られます。
発達障害は個人差も大きいため、同じタイプに分類されていても同じような症状があらわれるとは限りません。共通点としては、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点です。
あわせて読みたい
発達障害の症状
タイプによってあらわれる症状には違いがあります。また、個人差も小さくありません。例えば自閉症スペクトラム障害であれば、多くは1歳くらいから兆候があらわれ始めます。
「他人に興味を示さない」、「自分の興味のあることに何時間でも集中する」、「こだわりが強い」といった特徴があります。
大人になってから対人関係がうまく築けず、コミュニケーションがうまくとれないことで悩みを抱えて病院を受診し障害に気づくケースもあります。なかには子どものときに診断を受けることで、自分の障害についての指導やカウンセリングを受けて、障害とうまく付き合えるようになる人もいます。
注意欠如・多動性障害の場合は、落ち着きがなかったり、じっと座っていたり順番を待つことができない、うっかりミスが多い、集中力に欠ける、忘れ物やものの紛失が多くみられるといった症状が目につきます。
なかには大人になるにつれて症状が落ち付いてくる場合もあります。しかし、大人になっても症状がおさまらない人も多く、生きづらさを感じて、うつ病や不安障害を併発することもあります。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
発達障害の診療科目・検査方法
発達障害の原因
原因は明確にはなっていません。
生まれつき脳機能に障害があり、遺伝的なことがらも大きく関係しているといわれています。
よく、親のしつけや養育態度が原因で発達障害が生じるという誤解を聞きます。実際にそんなことはなく、発達障害はあくまで生まれついてのものです。
発達障害の予防・治療方法・治療期間
発達障害の根本的な治療法はまだ確立されていません。
対症療法として薬物治療をおこなうこともあります。発達障害を原因にしてうつ病などを併発している場合は、抗うつ薬などを使用することもあります。
そのほかの治療法としては、行動のパターンを整えていくことでストレスを減らす認知行動療法があります。ほかにも生活していくなかで課題をみつけて、その課題を1つ1つ解決していく「ブリーフサイコセラピー」などをおこなうこともあります。
治療期間は、個人差があります。多くは年単位での治療が必要となります。
発達障害の治療経過(合併症・後遺症)
治療をおこなっても発達障害の特性が著しく変わることはありません。
ただし治療をおこなうことで社会への適合性は高くなり、多くの場合はストレスの少ない生活が送れるようになります。
その結果として、本人も周囲の人も円滑に安定した生活を送れるようになることを治療の目的とします。
発達障害になりやすい年齢や性別
自閉症スペクトラム障害であれば1~2%、注意欠如・多動性障害であれば3~7%、学習障害であれば2~10%で発症しているといわれています。
男女比としては男性の方が多いとされています。
参考・出典サイト
執筆・監修ドクター
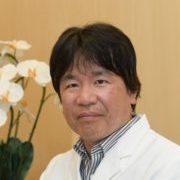
経歴昭和61年3月 青山学院大学文学部教育学科心理学専修コース卒業
平成6年3月 東邦大学医学部卒業
平成6年4月 東京女子医大病院で臨床研修を終え、
東京女子医大精神神経科入局
平成8年7月 武蔵野赤十字病院心療内科勤務
平成11年10月 しのだの森ホスピタル入職
関連する病気
発達障害以外の病気に関する情報を探したい方はこちら。
関連カテゴリ
発達障害に関連するカテゴリはこちら。
