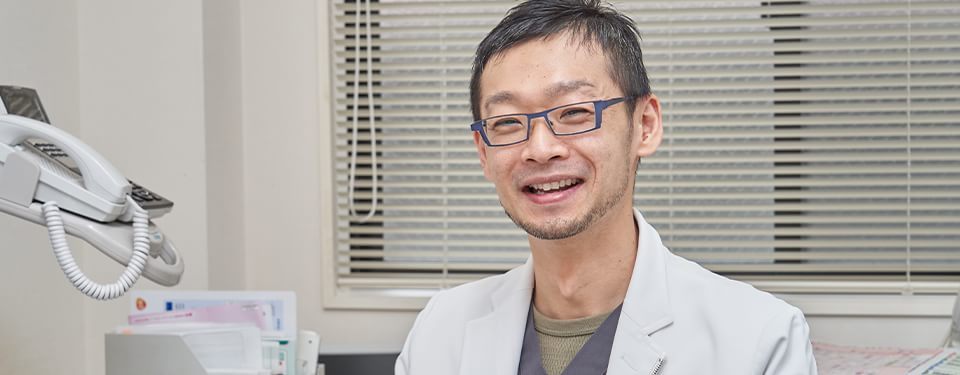 地域医療に貢献したいという想いを胸に、患者さまの健康と笑顔を支える医師
地域医療に貢献したいという想いを胸に、患者さまの健康と笑顔を支える医師
副院長
佐野 謙
取材日:2022年10月27日
佐野 謙先生(日本神経学会認定 神経内科専門医)にインタビュー
研修医時代に臨床の楽しさ・厳しさ・やりがいに触れ、神経内科の道へ進む
ご実家はクリニックだったそうですが、思い出やエピソードはありますか?

私の父も医師ですので、子どもの頃から父の診察している姿を見てきました。医療現場が身近な環境でしたので、誰にすすめられるでもなく、「医師の道に進む」という意識が自然とあったように思います。
今の医院は、新しく立て直したものなのですが、父の代の時は入院もできる有床の医院でした。実家兼クリニックという造りだったこともあって、実家に居た頃は病院によく遊びに行っていた記憶があります。当時は父の仕事に対してあまりつらそうな印象はなかったのですが、実際自分が医師になってみると当時一人で診療していた父もきっと大変だったのだろうなと感じるようになりましたね。
今の医院は、新しく立て直したものなのですが、父の代の時は入院もできる有床の医院でした。実家兼クリニックという造りだったこともあって、実家に居た頃は病院によく遊びに行っていた記憶があります。当時は父の仕事に対してあまりつらそうな印象はなかったのですが、実際自分が医師になってみると当時一人で診療していた父もきっと大変だったのだろうなと感じるようになりましたね。
神経内科の分野へ進もうと思ったきっかけがあれば教えてください。

大学時代は精神医学などに興味があり、どちらかと言うと臨床研究の方に進みたいと思っていました。ちょうど認知症が世間に浸透し始めた頃だったのもあって、いろいろ自分で本を読んで勉強したりしていましたね。
しかし、研修医になって患者さまの診察を担当するようになってからは、患者さまと接することの楽しさに触れ、研究職ではなく、臨床のほうにだんだん気持ちが傾いてきたんです。学生時代に脳神経外科など神経系の救命救急の実習があったのですが、その時意識障害の人や神経疾患の人をみたことがきっかけで、臨床をするなら、神経内科の分野に行きたいと思うようになりました。
しかし、研修医になって患者さまの診察を担当するようになってからは、患者さまと接することの楽しさに触れ、研究職ではなく、臨床のほうにだんだん気持ちが傾いてきたんです。学生時代に脳神経外科など神経系の救命救急の実習があったのですが、その時意識障害の人や神経疾患の人をみたことがきっかけで、臨床をするなら、神経内科の分野に行きたいと思うようになりました。
神経内科のやりがいや魅力は、どういった部分で感じますか?

神経内科は難しい、治りにくいというイメージを持たれがちですが、問診と診察だけである程度絞り込めるのが特徴です。そのため、ほかの科よりも問診を入念に行い、時間を割いていますね。
私を指導してくれた教授はパーキンソン病含めた運動障害疾患を専門にされていた方でしたが、神経内科の検査や手技はすべてやりなさいという指導方針でした。
その教えのとおり、いろいろな症例や検査手技を幅広く学ぶことができました。できないことや、知らないことが少ないというのは、医師になって仕事やキャリアを形成する上でとても役に立ったと思います。また、パーキンソン病のほかに髄膜炎や脳炎などの神経救急疾患の患者さまが大学病院に来られた際も、診療を担当する機会が多かったのですが、自己免疫性脳炎など難しい疾患もあり神経内科特有の知識も生かせる場だったので、 興味を持ちよく診療していました。
私を指導してくれた教授はパーキンソン病含めた運動障害疾患を専門にされていた方でしたが、神経内科の検査や手技はすべてやりなさいという指導方針でした。
その教えのとおり、いろいろな症例や検査手技を幅広く学ぶことができました。できないことや、知らないことが少ないというのは、医師になって仕事やキャリアを形成する上でとても役に立ったと思います。また、パーキンソン病のほかに髄膜炎や脳炎などの神経救急疾患の患者さまが大学病院に来られた際も、診療を担当する機会が多かったのですが、自己免疫性脳炎など難しい疾患もあり神経内科特有の知識も生かせる場だったので、 興味を持ちよく診療していました。
専門的な視点から原因を探り、わかりやすく丁寧な説明を大事に
しびれの診療をする上で、特に気を付けていることはありますか?

手足や全身、一時的なものや慢性的なものまで、しびれにはさまざまな種類があります。「今朝突然、しびれました」という方や「ずっと、しびれが続き紹介で来ました」という方など、一人ひとりのお悩みも異なります。問診を行う上で重視しているのは、慢性なのか急性なのかの判断を出し、症状が現れる範囲や場所を特定することです。突発的なしびれの場合は脳卒中や脳出血、脳梗塞、そして慢性的なしびれの場合は糖尿病やシェーグレン症候群などの代謝性疾患や自己免疫性疾患、手根管症候群や頸椎症などの整形外科的な疾患が疑われることが多いです。糖尿病などはそのまま当院で診ていますが、病状や原因によっては脳神経内科以外の科と連携し、紹介する場面もよくあります。
やはりどんな症状であれ、病気を絞るために問診が大切ですので、患者さまとお話する際はじっくりと時間をかけて、説明の際には分かりやすい説明をするように心がけています。言葉だけの説明では足りないので、後から見返せるように病状を記載したメモをお渡しすることもありますね。
やはりどんな症状であれ、病気を絞るために問診が大切ですので、患者さまとお話する際はじっくりと時間をかけて、説明の際には分かりやすい説明をするように心がけています。言葉だけの説明では足りないので、後から見返せるように病状を記載したメモをお渡しすることもありますね。
頭痛の相談では、どのようなお悩みの患者さまが多いですか?

頭痛でお悩みの患者さまのご相談で多いのはやはり片頭痛でしょうか。片頭痛の治療中だけど症状が改善しないという内容で受診される方も多いですね。診察や検査で重要なのは、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍などは命に関わる頭痛が含まれる可能性もあるので、それらを見逃さないようにすることです。痛みの程度がどれくらいなのかや、痛みが発症したときの患者さまの年齢なども重要になってきます。
50歳を過ぎてから頭痛が起こりだした場合は、片頭痛のような一次性頭痛ではなく別の疾患による二次性頭痛も疑われます。その場合は診察と問診をして別の疾患がないか確認を行います。頭痛の治療は薬物療法が基本となりますが、睡眠不足・睡眠過多、飲酒、食生活などが頭痛を誘発する原因のこともありますので、そのような場合は患者さまの生活環境や食事の好みをヒアリングして、生活習慣の改善に向けたアドバイスも可能な限り行っています。
50歳を過ぎてから頭痛が起こりだした場合は、片頭痛のような一次性頭痛ではなく別の疾患による二次性頭痛も疑われます。その場合は診察と問診をして別の疾患がないか確認を行います。頭痛の治療は薬物療法が基本となりますが、睡眠不足・睡眠過多、飲酒、食生活などが頭痛を誘発する原因のこともありますので、そのような場合は患者さまの生活環境や食事の好みをヒアリングして、生活習慣の改善に向けたアドバイスも可能な限り行っています。
パーキンソン病の患者さまに対しては、どのように対応されていますか?

パーキンソン病イコール難病と思われていますが、今はパーキンソン病の症状を和らげる薬が複数存在しています。そのため初診時には、患者さまに「難病のイメージは持たないでくださいね」と伝えています。また、一様にパーキンソン病と言っても症状は患者さまにより様々なので、その患者さまが困っている症状に対して作用のある治療薬を選択し調節することができます。
パーキンソン病については、今後さらに治療の選択肢の幅が広がる可能性がありますし、新たな薬が開発されると信じています。また、治療の説明のみならず、しっかりとお話を伺いながら介護されているご家族含めたメンタルケアも大切にしています。
パーキンソン病については、今後さらに治療の選択肢の幅が広がる可能性がありますし、新たな薬が開発されると信じています。また、治療の説明のみならず、しっかりとお話を伺いながら介護されているご家族含めたメンタルケアも大切にしています。
困っている人が気兼ねなく来られる、地域に根差した医院を目指す
今後、先生やクリニックが注力していきたいことはありますか?

今の症状がなかなか改善せずに困っている方や、どこに相談すればよいのか悩んでいる方を助けられる医院でありたいですね。当クリニックはどこにも看板を出していないのですが、地域の人や困っている人のいざというときに手助けができる存在になれたらと思っています。
当院は元々消化器内科ということもあり、私も脳神経内科の分野だけでなく高血圧症、糖尿病、喘息などの内科系疾患を診療する機会も増えました。ガイドラインに準じた治療を行い、地域のかかりつけとして幅広く対応できるように常に勉強を続けています。もちろん、当院で対応が難しい場合や詳しい検査が必要な時は、患者さまと相談しながら近隣の医療機関に紹介していますが、困った方が来院したときに対応できるような医院になれたらと日々努めています。
当院は元々消化器内科ということもあり、私も脳神経内科の分野だけでなく高血圧症、糖尿病、喘息などの内科系疾患を診療する機会も増えました。ガイドラインに準じた治療を行い、地域のかかりつけとして幅広く対応できるように常に勉強を続けています。もちろん、当院で対応が難しい場合や詳しい検査が必要な時は、患者さまと相談しながら近隣の医療機関に紹介していますが、困った方が来院したときに対応できるような医院になれたらと日々努めています。
神経内科の医師として、今後取り組みたいことがあれば教えてください。

今後は訪問診療にも力を注いでいきたいですね。これまで通院していた方々が動けなくなっても、住み慣れた家で心置きなく最期を過ごせるように、訪問診療を通じてサポートしたいと考えています。
現在、神経内科に詳しく、訪問診療の対応できる医師が不足している印象があります。地域の各エリアにそのような医師がいて、柔軟に対応できる環境になればいいなと思います。
現在、神経内科に詳しく、訪問診療の対応できる医師が不足している印象があります。地域の各エリアにそのような医師がいて、柔軟に対応できる環境になればいいなと思います。
地域の医療発展のために医院が目指していることはありますか?

CTの導入を検討しています。内科の診療を行う中で、やはりがんの発見の難しさを痛感しています。CTの検査が必要と感じたときに大きな病院にCTを撮りに行ってくださいとお願いしても、車がないなど、なかなか受診が難しい状況の方もいらっしゃいますので当院で検査が受けられればいいのではないかと考えています。CTは当院で、胃・大腸カメラは他のクリニックや病院で、というような形で医療連携を行いながら地域の患者さまのがんの早期発見率を上げるための取り組みができればと思っています。
困ってることや悩まれていることがあれば、お悩みに対して時間をかけて説明しておりますので専門的なことでなくても気兼ねなくいらしてください。これからもより多くの皆さまの健康をサポートし、地域医療に貢献できるように努めてまいります。
困ってることや悩まれていることがあれば、お悩みに対して時間をかけて説明しておりますので専門的なことでなくても気兼ねなくいらしてください。これからもより多くの皆さまの健康をサポートし、地域医療に貢献できるように努めてまいります。

