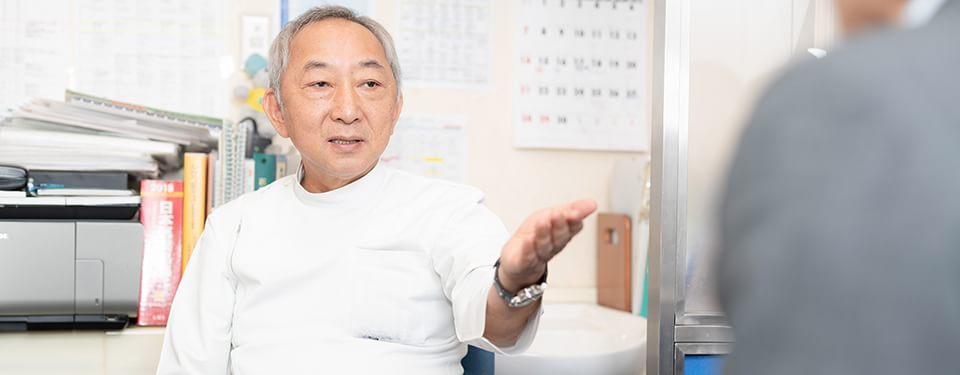 徹底したインフォームドコンセントと医療機器の活用で、納得の治療を提供。医師の歩みやこだわりをお聞きしました。
徹底したインフォームドコンセントと医療機器の活用で、納得の治療を提供。医師の歩みやこだわりをお聞きしました。
院長
大野 仁
取材日:2021年10月7日
大野 仁先生(日本眼科学会認定 眼科専門医)にインタビュー
ニーズに合わせた治療を提供できるよう、眼科の医師として研さんを積む
調布眼科医院を継承するまでの勤務医時代の経歴について教えてください。

大学を卒業した後は、東京慈恵会医科大学附属病院に入局し、最終的に講師まで務めました。そのほかに、東京慈恵会医科大学附属 第三病院や富士市民病院、東急病院、東京労災病院での勤務経験があります。
東京慈恵会医科大学附属 第三病院では眼科の医長、東京労災病院では眼科部長を務めました。特に長く勤務していたのは、東京労災病院ですね。勤務医として、様々な経験をさせていただきました。また、その他の取り組みとして、何号何等級と決まっている労災認定の基準を変更する役割を、3年ほど行っていました。
東京慈恵会医科大学附属 第三病院では眼科の医長、東京労災病院では眼科部長を務めました。特に長く勤務していたのは、東京労災病院ですね。勤務医として、様々な経験をさせていただきました。また、その他の取り組みとして、何号何等級と決まっている労災認定の基準を変更する役割を、3年ほど行っていました。
「日本眼科学会認定 眼科専門医」としての今後について教えてください。

白内障手術や硝子体手術、まぶたの手術などにオールマイティに対応するためには、「日本眼科学会認定 眼科専門医」の資格を取得できるくらいの知識や経験は欠かせません。
また、資格を取得したからといってそれで終わりではありません。資格を更新していくためには、毎年何十日間もの勉強が必要になります。日々の診療に加えてそのような勉強で知識を得ることは、「近くのクリニックで不安なく手術を受けたい」と考える患者さまのニーズに応えるものだと考えています。
また、資格を取得したからといってそれで終わりではありません。資格を更新していくためには、毎年何十日間もの勉強が必要になります。日々の診療に加えてそのような勉強で知識を得ることは、「近くのクリニックで不安なく手術を受けたい」と考える患者さまのニーズに応えるものだと考えています。
治療の精度を上げるために、技術の研さん・医学の進歩に応じた機器の充実化に努める
白内障・硝子体疾患・緑内障・眼瞼下垂などの手術に関して、特徴や強みはありますか?

どの手術においても、精度にこだわった手術を心がけています。例えば白内障手術では、シミュレーションシステムやサージカルガイダンスシステムを活用しています。シミュレーションシステムでは、手術後の見え方をシミュレーションし、患者さまのライフスタイルに合わせた見え方の希望を細かくお伺いします。サージカルガイダンスシステムでは、切開する場所や大きさ、そして手術中の乱視経線の精度を高めることができ、手術の誤差を少なく、どの症例にも一定にできるようにしています。
硝子体手術では、27G極小切開硝子体手術(MIVS)などに取り組んでいます。傷口が小さいため、術後の炎症を抑えられ、手術時間も短くなるというメリットがあります。緑内障手術においては、切開をせずに治療ができる眼科用パルスレーザー手術装置や、全長1mmのヘパリン使用眼内ドレーンを使用することで、体に負担の少ない低侵襲な手術を行っています。
硝子体手術では、27G極小切開硝子体手術(MIVS)などに取り組んでいます。傷口が小さいため、術後の炎症を抑えられ、手術時間も短くなるというメリットがあります。緑内障手術においては、切開をせずに治療ができる眼科用パルスレーザー手術装置や、全長1mmのヘパリン使用眼内ドレーンを使用することで、体に負担の少ない低侵襲な手術を行っています。
30年以上白内障手術をしていて感じる、変化などはありますか?

白内障手術は、医療技術の進歩により、これまでは病気でのマイナスをゼロに戻す手術だったのが、プラスへ戻す(老眼を改善する、乱視を改善して裸眼の視力まで上げていくなど)クオリティオブビジョンを考えた手術に変化しました。現在は「屈折矯正白内障手術」として、患者さまのご希望に合わせて、見え方の質を上げることを目指した手術になっています。
当院はその精度を上げるために、4つの手段を用いています。1つ目が「レーザー眼軸長測定装置」です。これを2台使い、精度のよい眼軸長を計測し、さらに細かい計算式を多用し詳細なレンズ度数を計測します。2つ目が「前眼部3次元OCT」です。これを使って角膜の前後面の乱視を測定しています。3つ目は「極小切開白内障手術」です。この手術をすることで手術の影響を減らし、さらに、「サージカルガイダンスシステム」を使って、切開する場所や大きさ、さらには手術中の乱視経線の精度を高めたうえで手術を行うことで、手術の誤差を少なく、どの症例にも一定にできるよう取り組んでいます。
当院はその精度を上げるために、4つの手段を用いています。1つ目が「レーザー眼軸長測定装置」です。これを2台使い、精度のよい眼軸長を計測し、さらに細かい計算式を多用し詳細なレンズ度数を計測します。2つ目が「前眼部3次元OCT」です。これを使って角膜の前後面の乱視を測定しています。3つ目は「極小切開白内障手術」です。この手術をすることで手術の影響を減らし、さらに、「サージカルガイダンスシステム」を使って、切開する場所や大きさ、さらには手術中の乱視経線の精度を高めたうえで手術を行うことで、手術の誤差を少なく、どの症例にも一定にできるよう取り組んでいます。
そのような変化における、眼科診療を行ううえでの課題などはありますか?

医学の進歩とともに上がる患者さまの期待に対し、どのように応えていくのかが課題になると思います。例えば、白内障手術をすることで、濁った水晶体を取り除き、見え方を改善させることはできます。ただ、眼にはレンズの役割をする組織として「水晶体」のほかに「角膜」もあります。2枚レンズになっているわけです。水晶体のトラブルを取り除いたとしても、角膜に何かしらの障害が起きていれば、「物が二重に見える」などのトラブルが起こります。
「白内障手術をすれば裸眼で見えるようになる」という情報が先走りすることで、白内障手術のメリットだけを見てしまったり、それ以外の病気によるトラブルが起こらないと勘違いしてしまったりする患者さまもいらっしゃいますので、そのようなトラブルを防ぎながらも、患者さまの期待にお応えしていく力が求められていると感じます。
「白内障手術をすれば裸眼で見えるようになる」という情報が先走りすることで、白内障手術のメリットだけを見てしまったり、それ以外の病気によるトラブルが起こらないと勘違いしてしまったりする患者さまもいらっしゃいますので、そのようなトラブルを防ぎながらも、患者さまの期待にお応えしていく力が求められていると感じます。
インフォームドコンセントを重視し、患者さまの納得のうえで治療を行う
患者さまに納得して手術を受けていただくための取り組みはありますか?

事前にしっかりと手術後の状態や治療内容をお話しするだけではなく、シミュレーションシステムを用いて画像をお見せすることで、患者さまにご納得いただいたうえで治療をするようにしています。医学の進歩により発生した眼内レンズの多様化に対し、シミュレーションシステムを活用し、眼内レンズの種類や仕組みを生活パターンや生活スタイルに合わせた内容で説明を行い、その他手術のメリットとデメリットなど、いいことだけでなく欠点もしっかりと説明するようにしています。
また、目の状態を様々な角度から計測できる機械を導入していることも、当院の強みの一つです。そのような機器を活用することで、術後の不具合や疑問にもしっかりと検査をしたうえでお応えすることができます。患者さまの疑問にしっかりと寄り添い、一つひとつ解消していくことを大事にしています。
また、目の状態を様々な角度から計測できる機械を導入していることも、当院の強みの一つです。そのような機器を活用することで、術後の不具合や疑問にもしっかりと検査をしたうえでお応えすることができます。患者さまの疑問にしっかりと寄り添い、一つひとつ解消していくことを大事にしています。
患者さまへ伝えたいメッセージがあれば、教えてください。

「医者を頼ってほしい」ということですね。目に関して何か不安なことや、「おかしい」と感じることがあれば、まずは眼科に足を運んでほしいと思います。インターネットにはたくさんの情報がありますし、ご友人などから治療について話を聞くこともあると思います。ただ、そういった情報が必ずしも正しいわけではありませんし、すべての人に当てはまるわけでもありません。
もし、医師に相談しても納得できないことがあるのであれば、納得のいくまでとことん聞いてもらえればと思います。医学は、算数のように「1+1」が必ず2になるわけではなく、人によってその答えは変わります。一人ひとりの患者さまに対し、その答えや、なぜそうなるのかをしっかりご説明しますので、ご自身で判断せずに一度ご相談いただければと思います。
もし、医師に相談しても納得できないことがあるのであれば、納得のいくまでとことん聞いてもらえればと思います。医学は、算数のように「1+1」が必ず2になるわけではなく、人によってその答えは変わります。一人ひとりの患者さまに対し、その答えや、なぜそうなるのかをしっかりご説明しますので、ご自身で判断せずに一度ご相談いただければと思います。

