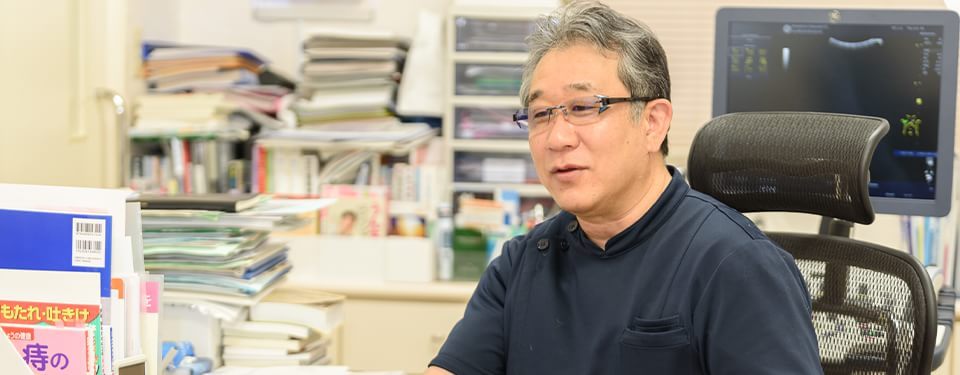 苦痛に配慮した内視鏡検査を行うことでがんの早期発見を目指す医師
苦痛に配慮した内視鏡検査を行うことでがんの早期発見を目指す医師
中島 真太郎先生(日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医)にインタビュー
苦痛に配慮した内視鏡検査を行うことでがんの早期発見を目指す医師

また、中学・高校は私立の一貫校に通っていたのですが、医学部に進学する生徒が多かったので、そういった環境の影響も受けていたかもしれません。
父はとても野球好きな人で、診療時間が終わると、野球観戦に連れて行ってくれました。キャッチボールにも付き合ってくれましたね。家の近くには、市民が利用できる市営の野球場があったので、友人たちともよく野球をして遊んでいました。身体を動かすことは好きでしたが、高校時代は帰宅部で特に運動はしていませんでしたね。子どもの頃のように、再びスポーツに情熱を注ぐようになったのは医学部に入ってからです。医学部では、ラグビー部に所属していました。

ラグビーの魅力は、個人の能力が特に突出していなくても、チームのメンバーがひとつになって協力すれば総合力で勝つことができるというところです。私が医師になって最初に専攻した外科は、チームの皆が一丸となって患者さまの治療を行うという点で、ラグビーに通じるところがあるように思います。ラグビー部時代に培った協調性は、チーム医療を行う上でも活かされたと感じますね。また、ラグビーで身に付けた体力のおかげで、長時間の手術も苦になりませんでした。
外科を選んだ理由は、診断、手術、治療まで一貫して一人の医師が関われる点に魅力を感じたからです。私が医学部を卒業した1991年当時は、現在ほど内視鏡が進化していませんでした。外科の医師と言えば当時の花形で、魅力を感じたのです。

そこで、何か得意分野を作りたいと思い、心機一転、東京の社会保険中央総合病院(現・東京山手メディカルセンター)に勤務し、大腸肛門外科や内視鏡について学ぶことにしました。34歳の時です。大腸・肛門疾患を得意とする先生の下につき、肛門の手術や内視鏡について研鑽を積みました。
3年間、教えを受けて、当初の目的は達成できたと思い、広島に戻ることにしたのです。最初は開業するつもりはなかったのですが、たまたま開業の話がとんとん拍子に進みました。その頃、父はもう既に引退しており、かつて開業していた場所は空いていました。そこで、同じ場所に新しくクリニックを建て、開業したのです。
目指すのは胃・大腸がんの早期発見。便秘は患者さまに合わせた治療を提案

誤解されている方も多いのですが、除菌治療を行っても、胃がん発症のリスクをまったくなくすことはできません。除菌治療後も定期的に胃内視鏡検査を行っていくことが大切です。ヘリコバクター・ピロリ菌に感染したことのある方なら、1年に1度は内視鏡検査を受けていただきたいと考えています。除菌治療をすればそれで終わりではないことを啓蒙していきたいと思っています。
胃がんは、すい臓がんや胆管がんのような発見が難しい病気ではありませんし、早期発見することで改善も期待できます。できれば20代のうちから胃内視鏡検査を受けていただきたいと思います。

大切にしているのは、個人のクリニックのレベルで切除できるポリープなのかどうか、基幹病院をご紹介する必要があるか否かを、限られた時間の中ですみやかに判断するということです。何でも自分のところで抱え込もうとするのはよくありません。そこの部分の振り分けをしっかりと行うことは、開業医が担っている大事な役割だと考えています。
これらの判断は、「日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医」として、これまで内視鏡検査と治療に携わってきた経験や知識が活かされるところだと思います。これまでの知見をもとに、内視鏡検査や超音波検査、血液検査の結果などから総合的に判断しています。

性別、年齢、腸の長さ、体質、服用している薬、生活習慣など便秘の原因はさまざまですので、患者さまに合わせたテーラーメイドの治療が必要です。便秘の治療では、患者さまとのコミュニケーションを大切にしています。一方通行の治療を行うのではなく、患者さまに細やかな問診を行い、薬の作用や現在の状態などを随時確認し、キャッチボールを行いながら治療を進めていきます。患者さまのフィードバックに応じて、お薬の種類や量を微調整する必要があるのです。
また、便秘の裏に隠れた疾患がないかどうか見落とさないようにすることも重要です。潰瘍性大腸炎、クローン病といった炎症性腸疾患や、直腸・肛門の病気が原因で便秘が生じている場合もあります。大腸がんやこれらの病気が隠れていないか、大腸や肛門も含めて注意深く診療を行っていきたいと考えています。
内視鏡検査のハードルを下げるため負担を軽減するさまざまな工夫を導入

大腸内視鏡検査も、鎮静剤や鎮痛剤を使用して行うことが可能です。スムーズに内視鏡を挿入することができないと、その後、しっかりと腸の中を観察することもできません。大腸は千差万別なので、できるだけ苦痛の少ないようその方に合わせた挿入の仕方を工夫しています。検査後のお腹の張りが少ないようにCO2送気装置も導入しています。
下剤も、患者さまによって飲みにくいと感じる薬が異なりますので、数種類ご用意しています。どの下剤が合ったのかを記録しておき、次回の検査の際に活用します。
また、次にいつ検査を受ければいいのかは、患者さまの状態によって異なります。画一的に次回の検査の時期を決めるのではなく、その方の状態に応じて、次の検査時期の目安をお伝えするようにしています。

また、肛門疾患や便秘にも引き続き注力していきたいですね。私は、「日本大腸肛門病学会認定 大腸肛門病専門医」の資格も持っています。大腸や肛門の疾患についても専門的な診療やアドバイスを行うことが可能ですので、ご相談いただければと思います。
そのほか、がんに関しては、既にがんと診断された方のご相談にも乗っています。他の医療機関でがんと診断され、今後の治療方法の選択について、他の医師の見解を聞きたいという方は、ご相談いただければと思います。がん難民となり、行き場をなくして困っていらっしゃる方の力にもなりたいと考え尽力しています。

「日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医」をはじめ複数の資格を維持していくのは大変なことですが、新しい知識を吸収するためにも役立っており、今後も知識のブラッシュアップを続けていきたいと考えています。資格を更新することで、他の先生方と情報交換できる機会も得られています。
私は広島で生まれ育ち、広島大学医学部を卒業しました。この地域の先生方には知人も多く、何かあった時でもご紹介がスムーズにできるかと思います。病気も、まず見つけないことには治療をすることもできません。ためらわずに検査を受けに来ていただきたいですね。

