心療内科

勤労者のメンタルケアを中心に、心と体の健康管理をサポート
当クリニックでは、開業以来、うつ病や適応障害、双極性障害、パニック障害、統合失調症、強迫性障害、物忘れから認知症まで、さまざまな症状をお持ちの患者さま一人ひとりと向き合い、一緒に治療を進めてきました。
憂うつな気分が続いている、何をするにも億劫で意欲がわかない、寝つきが悪い、またはすぐに目が覚めてしまう、疲れているのに眠れない、食欲がわかない、職場や学校でストレスを感じる、対人関係がうまくいかない、いつも過度に緊張してしまうなどの症状のうち、ひとつでも当てはまり、その状態が続いたり、症状が悪化したりしていると感じた場合には、一度当クリニックにお越しください。
どのような症状であっても通院すれば改善が見られます。診療では、患者さまやご家族の意向を伺いながら医師としてのアドバイスを行い、治療方法から改善に向けての流れまで一緒に考えていきます。
うつ病
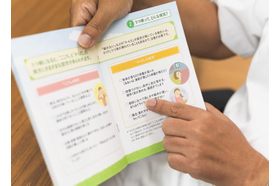
気分が落ち込むというように憂うつな気分で興味関心が低下し、心のエネルギーが低下している症状を「抑うつ気分」といいます。この抑うつ気分が強い状態を「抑うつ状態」といい、この状態がある程度以上で重症の場合をうつ病といいます。うつ病は、原因によって「身体因性」「内因性」「心因性」と分ける場合もあります。
また、一定の症状の特徴や重症度をもつ大うつ病性障害と、あまり重症でないが長期間持続する気分変調性障害と分けて考えられる場合もあります。
肉体だけでなく、精神的にも疲労困憊している状態の方は、うつ病になりやすいといわれています。しかし、上記の通り、うつ病といってもさまざまなタイプのうつ病がありますので、頼りがいのある主治医を持つことが大切です。当クリニックでは、薬による治療と生活指導をバランスよく行い、患者さまにとってより良い治療方法を一緒に考えながら治療を進めています。
適応障害
うつ病と類似している適応障害は、ストレスに適応できないためにさまざまな心身症状が表れ、日常生活をうまく送れなくなってしまう疾患で、ある特定の状況や出来事が、その人にとってとてもつらく耐えがたく感じられ、そのために気分や行動面に症状が現れるものです。
たとえば、職場で嫌なことがあったり、厳しいノルマを課せられたり、職場内でいじめやハラスメントにあった場合など、それが原因となって適応障害を引き起こす方もいらっしゃいます。
ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、その原因から離れると、症状は次第に改善することが多いのですが、ストレス因から離れられない状況では、症状が慢性化することもあります。そういった場合は、カウンセリングを通し、物事をリラックスして考えられる方法を探したり、ストレスフルな状況に適応するチカラをつけたりすることも推奨する治療法です。
治療方法は、患者さまの考えや希望を伺い、医師としての経験からアドバイスを行って、双方の意見を共有した上でより良い治療方針を一緒に決めていくよう努めています。
双極性障害
双極性障害は、精神疾患の中でも気分障害と分類されている疾患のひとつです。うつ病とほとんど同じうつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、これらを繰り返す慢性の病気です。
躁状態ではとても気分が良いので、本人には病気の自覚がありません。そのため、うつ状態では病院に行くのですが、躁の時には治療を受けないことがよくあります。しかし、うつ病だけの治療では双極性障害を悪化させてしまうことがあります。
患者さまの生活スタイルに合わせながら、副作用がなるべく少ない薬物療法と生活指導を行うことで、改善することが可能です。
治療をせず放置してしまうと、何度も躁状態とうつ状態を繰り返し、人間関係、社会との関わり、仕事や家庭といった人生の基盤に大きな影響を与えてしまうこともあるため、本人だけでなく周囲の人も、日頃の様子や気分の波を見守り、躁状態に気づくことも大切です。
パニック障害
不安障害は、精神疾患の中で不安を主な症状とする病気をまとめた名称です。その中のひとつがパニック障害で、不安障害を代表する病気といわれています。
たとえば、電車に乗っている時に気分が悪くなり電車を降りてしまった、という経験の後に、「また同じことが起きるのではないか」と不安になり電車に乗れなくなってしまう、といった状態がパニック障害の症状です。
治療では、患者さまからじっくりとお話を伺った上で、パニック発作をなるべく早く取り除く方法を一緒に探していきます。
統合失調症
統合失調症は、幻覚や妄想といった症状が特徴的な精神疾患です。家庭や社会生活を営む機能が障害を受け、感覚・思考・行動が病気のために歪んでいることを自分で認識できないため、他人とのコミュニケーションが難しくなります。
統合失調症は、およそ100人に1人弱がかかっている病気です。普通の話も通じなくなる、不治の病、という誤ったイメージを持たれている方も多いかもしれませんが、新しい薬の開発と心理社会的ケアの進歩により、改善が見られる患者さまもいらっしゃいます。
生活習慣病と同じく、大切なことは早期発見や早期治療、薬物療法、患者さま・ご家族の協力、再発予防のための治療の継続です。ご家族の皆さまにとっても、患者さまの状況をわからなければご自宅でのケアも難しいと思うので、当クリニックでは初診の際、なるべくご家族のご同席をお願いしています。長年にわたり人々の心の健康管理と向き合ってきた院長や臨床心理士やスタッフが当クリニックには在籍しています。ぜひ、気兼ねなくご来院ください。
強迫性障害
強迫性障害は不安障害のひとつで、強迫観念と強迫行為といった特徴があります。たとえば、鍵をかけ忘れてしまったかもしれない、ガスの元栓は大丈夫かな、と不安になり外出が困難になり、日常生活に支障をきたす場合もあります。
原因や発症に関わる要因は特定されていませんが、近年では、強迫性障害に対する有効な治療法がいくつかあります。個人差はあるものの、受診して治療が継続できた患者さまで、生活全般における支障の軽減や、社会的適応能力の改善も認められている方もいらっしゃいます。
強迫性障害は病気であり、性格や意志の弱さなどではありません。自分のために治療するという決意と目標を持って努力を続ければ、症状が改善する可能性は十分にあります。長期的な目標を持って一緒に治療に臨んでいきましょう。ご家族の皆さまにおいては、焦らず気長に見守ることが大切です。接し方も含め、話し合いながら改善に向けて一緒に進んでいきましょう。
物忘れ・認知症
認知症は、病気のような何らかの原因によって知能や記憶の能力が低下して、社会生活や日常生活に支障をきたす症状をいいます。記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を思い出したりする能力の障害)や行動に異常が見られたり、精神的な症状が現れたりします。
認知症や特にアルツハイマー病には、これさえすれば進行が止まるというような特定の治療法はありません。しかし、認知症予防という点では食事や運動が大切だと考えられています。さまざまな研究が進められていますので、ご本人だけでなく、ご家族の方であっても気になる場合は、一度当クリニックへお越しください。
大森西メンタルクリニックの基本情報
| 診療科目 | 心療内科 精神科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 |
東京都大田区大森西7-7-11地図
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間・休診日 |
休診日 木曜・日曜・祝日 土曜診療
10:00~13:00 15:00~19:00 土曜9:00~13:00 予約制 臨時休診あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 |
03-5763-7830 |
特徴・設備
| 待合室 |
|
|---|---|
| 設備 |
|
| 専門医 |
|
掲載している情報についてのご注意
医療機関の情報(所在地、診療時間等)が変更になっている場合があります。事前に電話連絡等を行ってから受診されることをおすすめいたします。情報について誤りがある場合は以下のリンクからご連絡をお願いいたします。
掲載内容の誤り・閉院情報を報告EPARKスタッフが見た
おすすめポイント
ポイント1
月・火・水・金曜は19時まで診療されています
月・火・水・金曜の午後は、15時から19時まで診療しています。19時まで診療しているので、日中はお仕事のある方も、お仕事帰りに通院しやすいクリニックです。
ポイント2
院長は日本精神神経学会認定 精神科専門医です
院長は、「日本精神神経学会認定 精神科専門医」の資格を持っています。うつ病、適応障害、双極性障害、パニック障害、統合失調症、強迫性障害などの相談ができます。
ポイント3
職場の悩みを相談できます
院長は、働く方々の心のケアに力を入れています。ストレスの要因ともなる職場の人間関係などのお悩みについてしっかりと耳を傾けてくれます。

