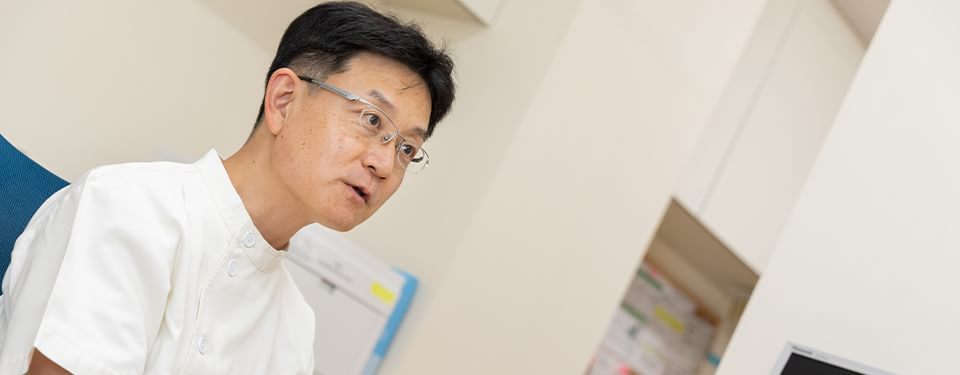 潰瘍性大腸炎の診療に注力、内視鏡検査の啓蒙でがんの早期発見を目指す医師
潰瘍性大腸炎の診療に注力、内視鏡検査の啓蒙でがんの早期発見を目指す医師
井上 拓也先生(日本消化器病学会認定 消化器病専門医)にインタビュー
米国での研究、大学病院での教育などさまざまな経験を積み開業の道へ

日本では、1980年に「角膜と腎臓の移植に関する法律」が施行され、脳死後の臓器移植の必要性も叫ばれていました。脳死判定基準や患者さまへの説明責任について話題になっていた頃だったのです。ジャーナリストの立花隆さんが『脳死』、『脳死再論』という本を出されていたので、当時、手に取ったのを覚えています。医学系の書籍をよく読むようになり、自然と医学部に進みたいと考えるようになりました。
消化器内科の道を選んだのは、内視鏡を通じて予防医学に関与したいという思いを抱いたからです。医学部を卒業したのは1997年のことで、今後は炎症性腸疾患が増えるのではないかと言われていた時期でした。炎症性腸疾患や大腸がんに興味を抱き、研究に携わるようになったのです。

現在では、腸内細菌と大腸がんや炎症性腸疾患の間には関連性があり、日本人の食生活の変化が腸の病気の発症に関与しているのではないかと指摘されています。こういった基礎研究を行ってきたことは、臨床の現場でも大いに役立っていると感じますね。上辺だけの説明ではなく、深い内容を患者さまにわかりやすい言葉に置き換えて説明をすることができるのは、研究をしていた時の経験が活かされているからだと感じます。
2年目で研究室を移動したのは米国の熾烈な競争の中で生き残れなかったためで、ある意味、挫折ではありましたが、海外で幅広い人生経験を積むことができたのも、患者さまと接していく上ではメリットだと今ではポジティブに捉えています。

開業し、患者さまと身近に接していると、今までのさまざまな経験が診療に活かされていると感じます。私は、防衛医科大学校出身です。現在では、志望している科目に関わらず、さまざまな診療科目で一通りの経験を積ませることが多くなっていますが、当時そういったローテーション制度を取り入れていたのは、防衛医科大学校だけでした。皮膚科や整形外科など消化器内科とまったく異なる診療科目での研修をした経験や、自衛隊病院で内視鏡検査に携わった経験、海外での経験は、今の診療にも活かされていると思います。幅広い人生経験があるからこそ、患者さまの辛い気持ちにも寄り添うことができているのではないかと思っています。
診療時は患者さまへの説明に力を入れ、内視鏡検査の啓蒙にも注力する

治療を行っていく上で大切なのは、患者さまへの説明です。胃食道逆流症が日本で増えている背景には、ピロリ菌感染の減少や食生活の欧米化があると説明し、生活習慣の見直しのためのアドバイスを行っています。避けた方がよい食べ物は、コーヒー、柑橘類、脂質の多い食品、刺激性のある食品です。飲酒や喫煙、夜遅くに食事を取りその後すぐ寝るという生活パターンも変えた方がよいでしょう。肥満の方は、ダイエットしていただくことで症状が改善される場合もあります。また、ストレスが原因で症状を起こしている方は、必要に応じて心療内科とも連携して治療を進めます。

とはいえ、大腸内視鏡検査は辛い検査ではないかと抵抗を感じている方も多いのではないでしょうか。そのため、細径のスコープの導入、鎮静剤の使用など、検査自体の負担もできるだけ少なくするように、さまざまな工夫を取り入れています。スタッフたちも不安を和らげるサポートや説明を心がけてくれていますね。
鎮静剤を使用するため、検査後はお車の運転を避けていただく必要がありますが、当クリニックは南海本線「松ノ浜駅」西口を出てすぐの場所に位置しており、電車でのご来院も便利な立地にあると思います。

治療を進める際には、米国で行っていた研究や臨床での経験を活かして、患者さまご自身にも病気のことを理解していただけるよう、わかりやすく詳しい説明をするように心がけています。患者さまには、治療を受けるだけではなく、自らも参加していただくことが大切だと考えているのです。当クリニックに通っている潰瘍性大腸炎の患者さまは血液検査の結果を見てご自身でデータを読み解けるほど、疾患に詳しくなっていますね。
治療は、ステロイド薬、免疫調節薬、生物学的製剤などお薬を用いた内科的治療が中心です。新しい薬も増えていますので、私自身も知識のブラッシュアップを心がけています。寛解しても再発することが多い病気ですが、「お腹の風邪をひくようなもの」とお伝えし、深刻に捉えすぎないようにご説明しています。
胃・大腸がんの早期発見によって患者さまに貢献することを目指す

内視鏡検査を受けていただくのであれば、このようにできるだけ見落としなく早期のがんも発見することで、患者さまにベネフィットを提供し貢献していきたいと考えています。内視鏡システムは、できる限り新しい機器へとアップデートするよう心がけており、2種のレーザー光によって粘膜表層の微細な血管や構造を強調して観察できるLCI/BLI機能を備えた内視鏡を使用しています。大腸内視鏡は、AI診断支援アプリケーションを搭載した機器を導入しています。大腸ポリープの可能性があるとAIが判断するとアラームを鳴らし、切除した方がよいかどうかまでアドバイスしてくれるのです。今後のAIの進歩にも期待していきたいですね。

若い世代の方には大腸内視鏡検査に抵抗があり受けたことがないという方も多くいらっしゃいます。しかし、症状が現れる前に定期的に大腸内視鏡検査を行って、大腸ポリープの段階で発見することができれば、こういったことは防げるのです。クリニックの患者さま、地域の皆さま方に対して、今後も内視鏡検査による早期発見の大切さについて、さまざまな形で提唱していきたいと考えています。

啓蒙活動だけではなく、病気の治療を進めていく際も、大切にしていることは、患者さまにきちんと疾患についての理解を深めていただくということです。これは、患者さまにも治療を行う一人のメンバーとして参加していただきたいと考えているためです。患者さまには、冗談交じりに「勉強してもらうよ」とお伝えしていますね。
潰瘍性大腸炎の患者さまの中には、とても難しい病気になってしまったと打ちひしがれてご来院される患者さまもいらっしゃいます。医師からの何気ない一言で患者さまの病気に対する受け止め方は変わりますし、治療に取り組む姿勢も変わると思いますので、患者さまが過度に心配しすぎないような説明をしていきたいと思っています。

